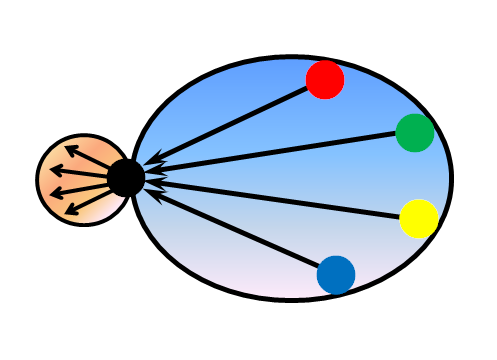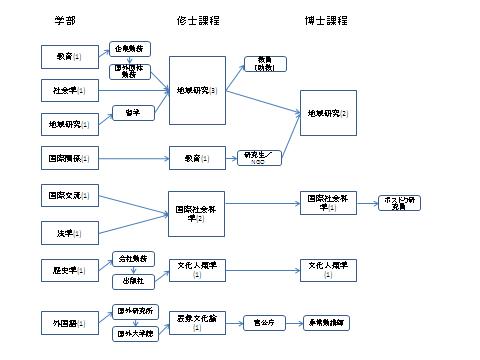研究会の記録(東京大・第2回研究会)
- 日時:2009年7月2日(木) 午後3時~5時半、午後6時~7時(談話会)
- 会場:東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム1
- 共催:共催:東京大学大学院地域文化研究専攻・アジア地域文化研究会
内容
趣旨
特定地域に関する地域研究ではなく、地域研究の方法論を大学でどのように教えるのか。あるいは、地域研究の方法論を身につけるための研究会をどのように企画するのか。この問いは、地域研究の資料や成果として非文字資料をどう扱うかを脇におけば、地域研究の方法論ではどのようなリーディングリストを用意するかという問いに置き換えて考えることができます。
「地域」をどのように区切るのか(たとえば「日本」「韓国」「中国」などのように区切るべきか「東アジア」としてまとめた方がよいのか、それとも別の区切り方がよいのか、研究テーマごとに適切な区切り方が違ってくるのか)という議論はあるにしても、特定の地域を研究対象とする人が集まったゼミや研究会では、研究対象に関して共通して身につけるべき知識や考え方のリーディングリストを作るのはそれほど難しいことではないでしょう。
その一方で、地域によらず研究テーマ別にリーディングリストを作るにはどうすればよいのか。ある研究者が自分の研究関心に沿ったリーディングリストを作ることはできますが(それができないと研究がはじめられません)、ここでも区切り方の問題が出てきます。どれだけの研究テーマに関するリーディングリストを集めれば地域研究の対象をほぼカバーすることになるのかという問題です。研究テーマを細かく区切ることは簡単ですが、区切った上でどうまとめるかも考える必要があります。さらに、研究テーマ別か手法別かなど、地域研究のリーディングリストを作る上で考えなければならないことは他にもありそうです。
地域研究方法論研究会は、いろいろな背景を持って地域研究に携わる人たちが、「研究者の広がり」「手法としての映像」「実践的活用」「地域の暗黙知」「文理接合」などの研究班によって地域研究の方法論を検討しています。その上で、各研究班の代表者が集まり、地域研究の方法論のあり方について検討しています。その際に、地域研究に関わる国内の大学を訪問して、地域研究に携わる教職員・学生の方々と一緒に検討を行っています。
この研究会では、事情が許す限り、各会場で2回の研究会を行うことにしています。2回目の研究会では、1回目の研究会で寄せられた会場ごとの参加者の関心や課題になるべく対応するような話題提供者を立てて、参加者のニーズにできるだけ沿った形で地域研究の方法論について議論したいと考えています。
東京大学駒場キャンパスでの2回目になる今回の研究会では、歴史学に基礎をおく地域研究のあり方、アジア以外の地域を対象とした地域研究のあり方、そして地域研究における実践と研究の関係を中心に地域研究について考えてみたいと思います。
この研究会はどなたでも参加できますが、地域研究に携わる大学院生や若手研究者の参加を特に歓迎します。
報告要旨
- 「地域研究の立位置の再検討──他ディシプリンとの競合・協力を超えられるか」(小森宏美)
地域研究は国際関係論と親和的な学問分野である、政治学とは競合関係にある、あるいは政治学の一分野である、など、地域研究に理解のある、もしくは地域研究者の顔も持つ研究者から、地域研究はこのように評されることが多いように思います。では、地域研究と他ディシプリンの関係を地域研究の側から見た場合にはどう語れるのでしょうか。他の学問分野での研究蓄積の豊富なヨーロッパ、そして冷戦終焉後、ヨーロッパの一員となった、しかしかつては地域研究の対象として欧米諸国とは分けられていた東欧諸国を事例に考えます。
- 「研究と実践の関係を問い直す──市民運動、アジア学、NGO」(福武慎太郎)
ベトナム反戦運動をきっかけに東南アジアへの関心を深めた人々は、あるものは研究(地域研究)へと向かい、あるものは実践(NGO)として東南アジアに関わり続けている。現在、NGOによる国際協力活動の現場では、市民運動の視点からNGOを捉える人々と、ひとつの開発エージェンシーとみる開発学や国際協力論を学んだ人々が混在している。地域研究を学んだ人々もまた、NGOを職場の選択肢のひとつとしてみている。このように世代や教育背景の異なる人々から構成される国際協力の現場において、研究と実践の関係はどのように考えられているのか、報告者自身の大学院教育、NGO経験をもとに考察を試みたい。
- 「フィールドはどこにあるか――地域研究者と社会の関わり」(西芳実)
研究者は論文を書くことを通じて社会と関わっている。そのことを踏まえた上で、ここでは研究活動を行なう過程で生まれる社会との関わりについて考えたい。たとえば、専門性や業種など異なる背景を持つ人びとと調査過程で情報交換を行なうとき、相手の求める情報の形と自分の情報の形が異なっていることにどう対応するか。あるいは、異分野・異業種の読者に論文が専門的でわかりにくいといわれたらどうするか。関心や目的、専門性の違いとして切り捨てるのではなく、自分のフィールドの範囲を捉えなおすことで対応する方法について考えたい。
質疑応答・討論
「暗黙知」をどう捉えるか
- 小森報告で暗黙知の例として塩川伸明氏の『多民族国家ソ連の興亡』を紹介している。「暗黙知」とは「その地域の事情をよく知らない人から見ると違和感があるもの」という捉え方ができると思うが、報告者はソ連に対して違和感があったということか。
違和感があったということではない。人間には、実際には知っていても本人も気づかない知識があり、それを暗黙知と捉えている。紹介した本ではソ連に関してその部分が言語化されていると思った。(小森)
- 3つの暗黙知のうち「地域の暗黙知」について。これを「知」としてしまうと、すべての人が共通してたどりつくべき1つの目標があるような印象を受けるが、観察者ごとにどこに到達してもいいことを強調するなら「見方」や「枠組」などの方が適切ではないか。
個人の有している知識、認識、理解、見聞などをまとめて「知」ということばを使ったが、それが「共通してたどりつくべき」という縛りを意識させるのならば、「暗黙的見方」のような言い方に変えることも考えてみたい。ただ、「枠組」→「結論」ではなく、「結論/結果」が出てはじめて、「ああ、そういうことに気づいて(
知って)いたんだ」とわかるようなことを「知」と呼んだ。(小森)
地域研究は現実の社会の変化にどこまで関わるのか
- 西報告で、被災者の行動について支援者と当事者のあいだに捉え方のずれがあり、それを地域研究者が読み解くという話は興味深かった。地域研究者の専門性がそこにあるということがわかった。
- 「被災前の状況を踏まえて被災後を理解する」と言うと、災害以前の社会が被災後も残って機能していることが前提となっているように聞こえる。被災者としては被災を契機に被災前の社会における資源配分のあり方を変える可能性があるのではないか。その可能性があるときに研究者としてどのように対応するのか。
被災前の社会を踏まえてその延長で見ると言ったとき、どのような「延長」の上で見ているか。たとえば「この村ではこの人が権威」という理解の単純な延長上で見ているのではなく、その社会ではどのような種類の人が権威を持つのか、その状況を人々がどう受け止めるのかを見ている。被災以前の状況をもとに被災後の行動を予測するのではなく、変化する部分と、変化するけれど根本では共通している仕組みを見ている。歴史的な経験の中で出てくるかたちを見ていて、できごとごとにどう変わるのかを見ている。見方がずれてしまう人たちは、その人たちの違和感の根拠が別の社会にあるのでこれと異なっている。日本社会やあるべき普遍社会に照らしておかしいと判断するために当事者の認識とずれてしまう。(西)
- 社会の中に変わるものと変わらないものがあるということか。
「社会の中の特定の部分は常に変わらず、別の部分は常に変わる」という形で固定的に捉えているわけではない。変わる部分と変わらない部分があること、変わっているように見えても仕組みとしては変わっていないかもしれないことなどを気にしながら観察している。作業の上では現場に行く際にこのあたりが変わっているのではないかなどと仮説を立てることもあるが、その場合でも固定的に見ているわけではない。(西)
- 「社会のあり方はこう変わる」という態度で臨むのか、「いろいろな方向に変わり得るがどこに向かうかはわからない」という態度をとるのか。
自分の例で言うと、研究対象は紛争地だった。紛争が起きないようになればいいと思っている。この地域の歴史を見ると、外の世界との関係が特定の勢力に押さえられやすいという弱みがあり、それに対する抵抗が繰り返されてきた。外部世界からの支援や介入を求めて、介入されやすい状況を求めようとする。20世紀後半には、「民族紛争」だとされると世界から注目されやすいという意識が働いたと考えている。この問題の解決のためには独占されない経路を作ることが重要で、そのため被災後には、外部からの支援者がいろいろな形で被災地と関係を作った方がよいこと、いろいろな資源を持った人が来た方がよいこと、直接の被災地ではなくても紛争地にも支援の形で介入した方がよいことなどを提案した。(西)
地域研究は対象社会の現状を肯定することになるとの批判
- 社会のあり方をいったん肯定した上で論述するということは、結局その社会の現状を肯定することにならないか。自分はマレーシアを研究している。マレーシア政治を普遍的なものさしで測ってそれに載らない価値を切り捨てるような態度ではなく、まずマレーシアで現実に動いている政治システムを把握しようとしているが、それをマレーシアで発表すると現政権を正当化するのかという批判を受けることがある。
研究者としての良心を総動員して表現するしかない。誰もが納得する意見はない。最終的には世界全部を敵にまわしたとしても自分はこのように考えるという態度で臨むしかない。もちろんその前の段階でそのように自信を持って主張できるような努力をすべきで、そのためには限られた資源や知識を総動員して自分の考えを組み立てる必要がある。(西)
実践での経験を論文にすることの難しさ
- 上智大学では地域研究を学ぶ学生がインターンでNGOに行く機会があるのか。
個人では何らかのインターンシップを利用して実践に関わりながら調査している。制度としては、イエズス会の難民サービスの場でインターンとして派遣してプログラムに組み入れられないかという話を大学院で検討している。(福武)
- 実践で身につけたことを論文にするときに問題が起こらないのか。自分は大学院に入る前に互助グループを作っていた。自分がディレクターだとみんなわかっているので、インタビューしたときに本当のことを言ってくれているかわからない。また、調査で取ってきたデータを論文に書くとき、NGOのメンバーを研究に利用しているのではないかという葛藤がある。それを超えたところで研究と実践の枠組みをどのように作ることができるのか。
自分にも同じような経験がある。NGOの開発と紛争下における人権侵害や人道援助を取り上げる運動があり、それに対して批判的な視点を取り入れて研究しているが、NGOを利用しているのではないかという批判は常に受けている。上智大学にはそのような批判を口にする研究者が多く、それに自分としてどのようにディフェンスするかを考えている。自分ではそれらの批判にもかかわらず意義があることだと考えていて、お世話になった人たちへの裏切りだとは思っていない。しんどいと思うことはあるけれど、自分とは異なるいろいろなディシプリンを持った人がいるなかで違和感を持ってそれを伝えてくれる人が身近にいるのはありがたいことだと思っている。人類学を専門にする人に話すとわかってもらえてうれしいけれど、わかってもらえない人に説明することも意味があると思う。(福武)
フィリピンのあるNGO研究では、フィリピンのローカルNGOについての人類学的調査をして、それを発表したことでローカルNGOから厳しい批判を受けたと本の中で書かれている。これはこの本の重要なテーマとして取り上げられている。英語で書いたために現地のNGO関係者にも読めて、自分たちが記述の対象にされたことに対して裏切られたという感情があったという。(福武)
論文よりもジャーナリズムの方が社会に有効に訴えられるのではないか
- NGOで国際ワークキャンプをやってきた経験がある。その活動は日本ではほとんど知られていないけれど世界的に知られているため、大学院に入ってそれを研究テーマにしようとした。でも、ボランティアやNGOは何となく学問にふさわしくないと思って別のテーマにした。研究すると論文を書くが、研究が使われるのはせいぜい政策だったりして、論文の内容は一般の人の手に届きにくいように思っている。あるいは、次の研究をするための研究になっているというイメージがある。だから、大学での研究では政策に近いものをやろうとしてEUを研究対象にした。現場に近いものにもとづいて、政策を離れた実践を研究課題にすることをどのように考えればいいのか。それをしたいのは社会に関わっていくためだが、社会に関わるのならジャーナリズムなどの方が学術論文を書くよりも直接的に社会に訴えられるようにも思う。長期的にアカデミックの場にいる人にもわかってもらいたいと思ってアカデミズムに身を置くことにしたけれど、それには時間がとてもかかるという印象がある。
NGO研究は地域研究こそが1つの分野にできるものだと思っている。グローバル化という現象を議論する上では地域という視点から人の移動や環境や難民を考える必要がある。一方で、地球規模の諸課題に対応するNGOがあり、地域という視点からNGOを見ることも必要になっている。今日の世界では地域を超えて普遍的な問題が起こっている。そのような問題は中央から見て周縁的な部分で問題が生じている。地域事情が十分にわかって調査研究する地域研究の手法は有効だと思う。(福武)
論文よりジャーナリズムの方がインパクトがあるのではないかという意見については、ある事実を多くの人に知ってもらうことだけを目的にするなら一般読者が読む雑誌で書く方がいいかもしれない。これに対してアカデミズムの意義はものごとの多面的な面をじっくり見ることで、その点ではジャーナリズムにできない部分がある。また、ジャーナリズムも結局はニュースで、注目されるニュースを追っていくという性格がある。ジャーナリズムでは取り上げられないけれど意味があるものを取り上げることも重要で、それはアカデミズムで引き受けられること。(福武)
即効性を考えるのなら週刊誌に書く方が意味があるかもしれない。ただし、即効性のある媒体は消えるのも早い。誰がどこに書くかということもメッセージとして伝わることを考えると、どこにどう書くべきかは課題によって違ってくる。研究者が新聞に原稿を書くこともあり、そう考えると、ジャーナリストと研究者ではどの段階で紙面がもらえるかという違いであって、新聞か大学かという違いではないのかもしれない。研究とは論文を書くことだが、大学でやっているのは論文を書くことそのものではなく、ものの見方を身につけること。大学院で学んだからといって常に研究の枠の中で発信しなければならないわけではない。社会への働きかけ方はさまざまで、ものの見方を身につけるのが大学。別の言い方をすると、他人に共有される形で提示する方法を学ぶところが大学。(西)
地域研究者は仮説群や概念を共有しないのか
- 小森報告で「地域研究には独自の方法論がない」と言っていたが、政治学でも「ディシプリンがない」と言っている。経済学や社会学や歴史学など他の学問分野から理論を借りていて、政治学独自の理論はどこにあるのかと議論している。だからといって政治学という括りが無意味なものだとは思っていない。政治学をしている人たちが共有している仮説があり、共通の概念がある。共通の方法論があるというよりもそこにまとまりの核があるのかと思う。地域研究では共有されている仮説群や概念はないのか。
自分の理解では地域研究者は共有する仮説群や概念を求めていない。まず仮説や概念があってそれを研究するという方向では進んでいない。西さんのように災害現場での関わりや柳澤さんのように自然科学と人文社会科学の接合を考える上では仮説群や概念が事前にあるかもしれないけれど、一般的には地域研究者が出発点として何らかの概念を共有することはないと思う。ただし課題はあるので問題設定を共有することは可能。研究する上でのトレンドのようなものは何となくある。地域研究は国や地域と関わるけれど、社会の中でどの問題を扱うかを気にするという特徴があり、現代社会との関わりで出てくる問題に関心がないわけではない。(小森)
- 国や地域との関わりとはどういうことか。地域研究における共通の概念や課題が国や地域に依存するのであれば、他の地域を研究している人との間で議論はできないということか。
そうではない。特定の狭い地域について見ていてもそれを通じて世界のことを見ているため、他の地域を研究する人と合同で研究することもできる。(小森)
共通する仮説群や概念があるかないかということと、それが目に見える形で提示されているかどうかは分けて考えるべき。小森さんが「仮説がない」と言うのは、問いに対してあらかじめ答えの方向を決めてから研究するわけではないという意味だろう。最初はそうだとしても、その課題に対する答えが積み重ねられていくので、地域を超えて地域研究者に共通する仮説群や概念は存在するはず。それが言葉で書かれたものとしてまとめられていないので存在しないように感じられるということではないか。ただし、共通する仮説や概念があると言ってもすべての地域研究者に共通する仮説や概念があるということではなく、関心などによっていくつかのまとまりに分けられて、そのなかで共有される仮説や概念ということになると思う。(山本)
地域研究者に共通の仮説や課題はあると思う。それを記述する言葉を揃えようとする方向に向かっていないにしても、同じ課題について話しているし、わかりあえる。それがあまり積極的に記述されていないのは、地域研究者には個別の論文にそれを読み取る力があるはずだから。先行研究を自分の関心に沿って整理すると、自分が関心を持っている課題に対してそれぞれの研究者が論文を通じて議論を積み重ねている様子を見て取ることができる。その意味では先行研究のセットは1つの課題に対する仮説群になっている。このような課題の1つ1つを言語化して並べておく制度化がなされていないため、課題や仮説があることが目に見えにくい。存在はしているけれど、それをあえて整えようとしていないのが地域研究だと言えるのではないか。このことは、逆に言うと、言葉を揃えていなくても共通の課題や概念をとりだすことができるということであり、したがって目に見える形で提示されていなくても共通した課題や仮説はあるという話になる。(西)
言葉であえて表現しないようにしてきたとすれば、その背景として、課題は共通していても現実社会では時代や地域によってその課題の表現のされ方が異なるため、あえて揃えないという考え方が働くのかもしれない。また、地域研究では現在進行中の課題への取り組みも積極的に行われるため、最先端の関心事を並べようとすれば十分な研究が出ていない状況で課題をまとめなければならず、それが大変なのではないか。これに対応するには、個人としては日々の情報収集の中から関心のあるものを選んでいくしかないだろうし、もう少し制度化したものとしては、地域研究者が関心のある課題を持ち寄る方法もある。たとえば雑誌『地域研究』で特集企画を募集しているのはそれを発表する場の1つとして捉えられる。(山本)
他の学問分野の「言葉づかい」を身につけること
- 学問の方法を身につけることは外国語を学ぶことに似ているように思う。たとえば国際関係論の研究者と話をするときに、国際関係論で共有されている概念を使って話されるので、それを知らないと話が通じない。他のディシプリンでどう位置づけられているかを知っていくことは重要。少し本を読んだだけでわかることではない。
特定の言葉群を共有しているサークルがあるということと関係していると思う。地域研究にディシプリンがないという人もいるが、その人たちを含めて共有する考え方はある。自分の考えていることを必ずどこかに位置づける。これを身につけないとだめで、どこにどう乗せていくかは考えざるを得ない。(西)
地域研究では人類学や宗教学など広く浅く各ディシプリンの思考をある程度知っていた方がいい。また、地域研究の特徴の1つは懐の広さ。いろいろなディシプリンをうまくコラージュして1つの物語を作り、理論とは違う形のストーリーを描けるのが地域研究。ただし、このことをディシプリンとして教えるとなると、じゃあおもしろい方がいい、理論ではだめだと勘違いされるので教えることも伝えることも難しい。(新井)
他のディシプリンをについて一通り知っておくのが戦略として重要だというのは賛成。ただし、すべての学問について事前に基本概念を身につけておくことは無理。それに、たとえば政治学と経済学のように既存の学問的ディシプリンどうしが対話するときにはどうするのか。そんなことを考えると、その場その場で共通の話し方を探り当てていくしかないと思う。先ほど出たので国際関係論を例にとるが、国際関係論を学んでいる人は、家庭内でも買い物するときでも遊びに行くときでも国際関係論の用語で話しているというわけではなく、相手応じて通じる言い方をしているはず。こちらはそれらの用語を学んでいないので、わかる言葉で話してくれとお願いするしかない。それがうまくいかないとしたら、理解できない受け手と説明できない話し手の両方の勉強不足という話になる。ある専門分野の用語がわからないからといってその専門分野で考えている理論が全くわからないということにはならない。もしそう考えているとしたらそう考える人の知的怠慢。(山本)
「自信のない地域研究者」をどう考えるか
- 小森報告では地域研究が他分野の研究に対して従属的な扱いを受けるように感じることが指摘されていたが、地域研究が他人の土俵で従属的な位置づけを受けていたとして、それ自体が悪いことだとは思わない。それよりも、地域研究を行っている学生のあいだで自分のやっていることに自信が持てなくなることの方がずっと問題だろう。それを解消するための働きかけが「地域研究にはディシプリンがある」と言い、その中身を提示すること。これとは別に、どうして地域研究者は自分に自信が持てないのかと考えると、研究内容や成果を相互に認めあうサークルが制度化されていないからであって、個別の地域研究者の研究内容のためではないのではないかと思う。(山本)
「地域研究に自信がない」について。どうして自信がないのかを考えたとき、問題は教員にあるのではないか。教員が「地域研究にはディシプリンがない」というディスコースを作っている。現在の地域研究の教員の多くは、今は地域研究をすると言っているけれど、自分たちは地域研究以外に何らかのディシプリンを持っている。(福武)
地域研究を専門にしている学生たちに対しては「ディシプリンがある」というメッセージを発するつもりでこの研究会を立ち上げた。ただし、実際にはさまざまな形で地域研究に関わっている人がいるため、「地域研究はディシプリンである」というと、既存のディシプリンと地域研究のあいだで選択を迫るような局面が生じてしまう恐れがある。地域研究の多様性をなるべく広く確保するため、そういう場では「地域研究はディシプリンである」という言い方をあまりしないように心がけている。ただし、ディシプリンであるかないかとは別に、地域研究として行われていることに方法はあるのだから、それを括り出して、地域研究を学んでいる学生に提示することには意味があると思っている。(山本)
地域研究にディシプリンがないから自信が持てないと言っている人がいることは悪いことだとは思わない。根拠のない自信や、自分自身の研究能力とは違うところに依拠する自信はよくない。自分は地域研究にこだわる必要はないと思っていたが、前々回の研究会で「なぜ地域研究と呼ばなければならないのか、事例研究でいいではないか」という質問を聞いて、単なる事例研究ではなく発信するだけの議論があるのだから地域研究と呼ぶべきだと思い、自分に地域研究への思いがあることを知った。事例研究は決定的に見て研究している。そういう形で研究するよりも、地域研究のようにいろいろリスぺクトする誇りがあった方がいいように思う。(福武)
「自信がない」の意味が、自分の持っているものに価値があると認めた上で、それが他人にも無条件で価値があると受け取られるはずだとは考えないという態度を指すのであれば、その考えには同意する。ただし、「自信がない」といったときに自分が持っているものの価値自体に自信が持てない場合もあり、そのような人が無理に「自信」をつけようとするときに取り得る行動として、研究を狭く区切って、その外側や境界線上にある他の研究活動に攻撃的になることがあるように思う。その結果、「NGOの研究は社会活動であって研究ではない」とか「映像資料を使うのは遊びであって研究ではない」というような言い方が出てくる。これは自分の研究に対する自信のなさが裏返しになって他者を攻撃している例だと考えられ、この点では「自信がない」ことが問題になることもあると思っている。(山本)
地域研究における映像実践の現状と今後の展望
- 映像は解釈の幅が大きいのではないか。
それは映像を使った研究が批判されるポイントの1つ。民族誌映画だとなるべく解釈の幅を広げなくする文法がある。たとえば、距離感がある映像にすること、ナレーションや字幕を入れること、時系列的に編集すること、よくわからないカットを入れないことなど。ただしこの文法を使って撮られた映画はあまりおもしろくない。(新井)
- 論文だと「この論文では○○の事例を取り上げる」などの前置きがあり、そこで扱われる事例の背景などが事前に説明される。これに対して映像では、たとえば暴動の映像だけ発信することがある。このような方法では背景的な知識がない人は強烈な受け止め方をするのではないか。バランスのとり方はどう考えるのか。
ニュース映像では速報性とインパクトが大事なのでそのまま使う。ドキュメンタリー映画では作り手の主張がかなり入ってくることが多い。その場合、主張に従ってインパクトのある映像を効果的に使う手法がとられることもある。研究者が映像を使う場合、暴動を自分の主張に従って過度にインパクトのある使い方をしたら減点の対象になる。(新井)
- 解釈の幅を広げないようにするということは、たとえば監視カメラの映像だと満点を取れるということか。
監視カメラの映像は撮影された人の肖像権の問題があるので利用が難しい。(新井)
- 監視カメラそのものではなく、被写体に同意を得た上で固定カメラで撮影したらどうか。
撮影されたものにストーリー性がないために評価は低くなる。被写体に意識させないでカメラをまわすのはかなり高度なテクニックが必要になる。(新井)
- 改めて、民族誌的映画とはどういう映画を指すのか。
撮影者が透明人間的なものもある。撮られる人との人間関係もある。オーソドックスなものとしては、撮影する側がされる側と距離感を持って撮る。人類学的な成果として評価されるにはさらに被写体の同意を得ていることが必要。(新井)
- 民族誌的映画は映画的文脈で編集されることになるのか。そこに手を加えるときに編集した人のストーリーが入ることにならないか。
最近ではわざとポエティックな映像をとることも流行っているが、ここではオーソドックスな方で答えることにする。映像の視聴者はテレビなら視聴者、研究の映像なら研究者。研究の映像も、テレビのように飽きないおもしろいものを作るような考慮はしない形で編集することはある。研究班で扱った南出作品は儀礼を撮ったもので、これを見るとオーソドックスな文法がよくわかる。川瀬作品はそれと正反対で、対象とのやり取りを積極的に取り入れる構造になっている。ふつうの子どもを撮ったものなので、人類学的映画の潮流の中ではおもしろいと評価されるけれど、ふつうに見た人はどんな意義があるのかわからないと思うかもしれない。しかし人類学の制作理論にのっとって撮ったものなので高く評価される。(新井)
- 学術成果としての映像に話を絞ったとき、それが映像でないといけない理由は何か。論文で書いてもいいのか。方法論上で映像である必然性はあるのか。
それは常に言われている批判。実際に映像がなくても研究はできる。しかし映像メディアが普及して大きな影響を与えている現状を考えるならば、映像メディアの扱い方について考える必要がある。(新井)
- それだと映像メディアのことを考えるときに自分自身が映像メディアの中に入ってしまっていることにならないか。
方法論の研究会でもあるのでどのように映像を利用して研究するのかも検討している。研究班では、基本的に参加者が撮影して、その映像を使うこともあるし、使う際にどう使うかを考えたりしている。映像という有効な資料があり、それを使わないのはもったいない。それなら映像を有効なツールとして使うべきではないかと考えている。映像ではなくてもいいかもしれないという前提を受け入れてしまうと、どうして映像が必要なのかを考えなければならなくなる。そう考えるのではなく、すでに映像がこれだけ普及しているのだからその利用の手法を構築しようと考えている。(新井)
- 先ほどの質問と重なるが、映像固有の問題はどこにあるのか。
解釈の幅を持たせないこと。映像は解釈の幅が広いために危うい部分が多いことでも批判され、学術研究に向かないとよく言われる。そのため、研究班では映像を資料、分析、表現の3つに分けて捉えている。この3つのうち表現の部分がしばしば問題とされる。(新井)
- 「資料」と「分析」の違いがよくわからない。
行為に着目して分類したもの。「分析」とは分析として使われる映像のこと。映像だと録音したりメモしたりする手法よりも分析しやすいので、そのために映像を使うことができる。「資料」は、たとえば貴重な儀礼の映像を撮ったりしたもの。(新井)
- 撮られたものはどれも資料ではないのか。それが利用されると分析という区分にも入れられるのが重複している感じがして不思議な気がする。1つの映像が資料になったり分析になったりするのか。
重なる部分もあるけれど、映像について話すときにはこの3つに分けて話すとわかりやすい。そこからさらに「発見」などに分けていくこともできる。実際には分析したら終わりのような映像を資料として保存していくほどの余裕がない。(新井)
- 改めて、映像メディアの特殊性は何か。
アーカイブ化に金がかかること。書籍と比べるとアーカイブ化が簡単にできない。分析に使って終わりにしたとき、それを資料として置くとみんなが使えるようになるが、それができないので、資料とする映像とそうでない映像を区別することになる。(新井)
- 一方で客観性の重要性が強調され、もう一方で民族誌的映画のように撮る人のストーリーの必要性が言われているけれど、両者はどう折り合うのか。
想田監督は観察映画を作っている。隠しカメラとは言わないけれど、客観的な映像を目指している。それは学術映像に近い。学術映像にしたときは何らかの理論的な裏付けがないと評価されない。(新井)
- 民族誌映画では表象の政治性をめぐる議論はしないのか。
その点について日本はかなり緩い。海外では表象についての議論はほとんどがその議論になっている。(新井)
- 客観性が必要だというが、解釈の幅がある方が多様な声が表象可能になるので高く評価されるとはならないのか。
多様な声が表象されてしまうという批判を避けるため、被写体にインタビューしているところを映像に入れる手法がある。ラポールが築かれていることを映像に入れると得点が高い。いろいろな人がいろいろな解釈をする可能性については、その可能性について考えるよりも、いろいろな人が自分自身で表象できるようにする方がいいという流れの方が強い。(新井)
- この研究班で目指している方向は何なのか。映像を使って何かしろという課題が与えられたために対応しているだけのように聞こえてしまう。関心はどこにあるのか。
映像を学術研究で有効なツールとしてきちんと根付かせたい。(新井)
- 重要なのは発信力か解釈力か。肝心なのは解釈力の方ではないのか。映像を読み取るディシプリンを身につける方がアカデミックな形にできるように思う。「研究のツールとして根付かせたい」というとき、現状ではどの部分が足りないと思っているのか。
映像地域研究の手法開発では歴史学の文献作法を参考にして映像資料を根付かせる作業をした。それと別に、表現として映画を作る場合には客観的な映画を作るということがある。(新井)
- 映像人類学は人類学をベースにしているものと思うが、言葉で表現する場合を含めて、人類学全体の傾向として解釈を極力排して客観的な記述を求めるということか。
考え方や態度はいろいろあると思う。その中には楽しい方法もあるだろうが、そうは言っても結局は客観的なデータを取っていないと批判されて減点される。民族誌を書くときには使えないことが多い。(新井)
- 手が付けられていない映像がたくさんあるのでそれを使う方法を考えたいというが、これまで手が付けられてこなかったとしたらもしかしたら意味がないために誰も手を付けてこなかったのかもしれない。実際には「そこにあるから」がきっかけだったとしても、それに取り組む上では何のためにやっているのかを意識しなければならないのではないか。「映像でなくてもいい」と言われると、その程度のものなのかと思ってしまう。
- 自分もフィールドで映像を撮っているけれど、映像と論文でできることは違うと思っている。多様な解釈を開くことこそ映像ならではの利点だと思う。たとえば音やビジュアルの組み合わせ。マテリアルなものをメタファーでつなぎあわせることができること。そういう意味で映像と論文には扱える領域が異なっていると思うが、映像と論文をどのように使い分けているのか。
映像には音やビジュアルのように論文とは違う効果もかなりある。昔はフィルムで一部の人しか撮れなかったけれど、今は誰でも撮影できる。そのため、映像によって「人類学的な知」が民族誌を含めて変わる可能性がある。音やビジュアルにイメージを含める民族誌のあり方が理想的だと思う。さらに進むと、民族誌映画でインタラクティブなものが望まれる方向が出ている。もっと使いやすいコンテンツを作りたいということもある。(新井)
- 宗教研究をしているということだが、映像では言語以外のものが映り込むことで分析上の利点があるということはあるか。
インタビューのときに表情など言語以外のメッセージが読み取れる。ただし弊害も多い。映像は個別性のものなので、その場で撮れた言葉を使うのが適しているかという問題がある。また、映像だと盛り込まれる情報が多いために誤解を招く可能性もある。たとえば表情のせいで発言内容が勘違いされることもある。(新井)
- 自分の経験では映像を編集するなかで理論が見えてくることがある。それについてはどうか。
確かにある。撮った映像を見て発見したことも何度もある。(新井)
研究会を終えて
- 討論後の感想
参加者の方々の感想からもわかりますように、今回の談話会のおかげで、映像に関するある程度の知識を共有していないと議論がかみあわないことがよくわかりました。ほぼ知識を共有するための議論で終わってしまったと思います。映像活用についてまだまだ認知度が低いために難しい課題ではありますが、映像活用を根付かせるための「他流試合」の型をもっと磨く必要を痛感しました。その意味でわたしとしては多くのことを学べたので、とても意義のある談話会でしたが、参加いただいた方々に不完全燃焼の思いをさせたことをお詫びいたします。また、そうした状況下で極度にわかりやすく説明したために、談話会のやりとりを文字化したものをみると、「言い切っている」調子で誤解をまねく表現が多々あると思いました(客観性の話や、映像ジャンルによる映像内容の特徴、評価基準など)。ただ、この点でおもしろいと思ったのが、もしわたしがしゃべっている様子を、あの文字化したものとともに動画で配信したら、あの文字から伝わるものと、また違った印象と意味内容を伝えることになるだろうという点です。感想のなかで、映像上映がなかった点への不満がありましたが、映画などではなく、こうした身近なやりとりを実験材料として記録・上映し、映像メディアの特性について考える講習があっても面白いと思いました。ちなみに、資料的活用については、おもに記録・保存を目的とした映像の活用の仕方ということです。分析的活用は、おもに分析を目的とした映像の活用の仕方ということです。当然、あとの表現も含めてそれぞれの活用の仕方と、そこで活用される映像内容はかぶったりします。(新井一寛)
- どの学問分野も自分に自信がない
地域研究方法論研究会を進めてきた前提に、地域研究には確立した方法論(ディシプリン)がないという現状認識がある。既存のディシプリンのフロンティアの部分が地域研究なのだから、地域研究に確立した方法論がないのはあたりまえだ、となっていたように思う。そのため、地域研究のアイデンティティは常に問われることになるし、そのような不安定な状態こそが地域研究の地域研究たるゆえんだ、というような考え方が出てくることもある。そのようなあいまいな地域研究のあり方を通底する思想のようなものを抜き出すならば、「現代世界が抱える諸課題に対する学術研究を通じた取り組み」というのはよくできたまとめになっていると思う。
ところが、学問分野としてのアイデンティティに自信がないのは地域研究だけでないらしい。
たとえば政治学の概説書を開くと、序章で「政治学のアイデンティティ」が語られている 。加茂利男ほか編『現代政治学』(有斐閣、2007年)の序章の構成は、「1.政治学の位置―大学の中で、社会の中で(学部をつくれない学問?/メシのタネにならない学問?)、2.政治と政治学―決定と行動の科学(マンハイムの問い/現実科学としての政治学)、3.ディシプリンとしての政治学(自己完結しない学問/モザイク上の科学/もう一つの政治学)」となっている。この中で加茂は、「政治学の仕事は基本的には、・・・・法則的・歴史的・思想的な知識を政治の世界に提供すること」としたうえで、「学問である以上、科学性をあいまいにして政治的・イデオロギー的な「べき」論にのめり込むわけにはいかず、半面、政治という決定・行動をめぐる現象についての学問である以上、現実政治の臨場性・実証性と接点をもたないひからびた学問でいるわけにもいかないという、厄介な性質を持っている」と書いている。さらに、学問としての自信の有無は、教育・研究の場(つまり教科書や学科・学部、学会、学会誌)や就職の場が制度化されているかどうかによっており、単独で学部をつくれず、専門職に直結しない政治学は「教養」の性格が強く、法学や医学と比べて自信がないという。そんな政治学の拠り所は、(1)現実社会への問題意識、(2)科学性、(3)未来志向あるいは実用(実践)性とされる。前掲書の「おわりに」には、「現実の政治を科学的に分析する目と新しい政治のあり方を描き切る力、この二つは政治学にとっての車の両輪」「人間社会の重層的な危機に対して、私たち一人一人の真剣な営みが現在求められている」「政治学は、この協働の形成と公的解決の方法をめぐる知的な営み」と書かれている。また、「政治学だけでこれらの危機に対処する処方箋を出すことはできない。他の学問との協働が必ず必要」とされるなど、課題の全体性も意識されている。
比較的新しい学問分野であることを自認する社会学も同様だ。稲葉振一郎『社会学入門――〈多元化する時代〉をどう捉えるか』(日本放送出版協会、2009年)は、「社会学における教養教育ならびに導入教育においては、確たるフォーマットがない」という現状を踏まえて書かれている。そこでは、「世界の側から社会学を見る」ことを通じて「社会学の固有のアイデンティティ」探しが試みられ、社会学の理論とは何か、社会学が何の役に立つのかが検討されていると書かれている。
学問分野としては伝統のある歴史学でも、それが何であるか語ろうとするならば、その学問としての始まり、意義、社会の役に立つかどうかを見ることになる。佐藤卓己『ヒューマニティーズ 歴史学』(岩波書店、2009年)の構成は、「1.歴史学ゼミナールの誕生―歴史学はどのように生まれたのか、2.接眼レンズを替えて見える―歴史学を学ぶ意味とは何か、3.歴史学の公共性―歴史学は社会の役に立つのか、4.メディア史が抱え込む未来―歴史学の未来はどうなるのか、5.歴史学を学ぶために何を読むべきか」となっている。
こうしてみると、どの学問分野も「現代世界が抱える諸課題に対する学術研究を通じた取り組み」を行なおうとしている点は同じだとも言える。どの学問分野も成り立ちの部分と最先端の部分があり、最先端にいる人は、新しい手法や課題をそれまでの手法や課題の延長上に位置づけながら新しい分野を切り拓いている。最先端部分どうしを比べたなら、地域研究とほかの学問分野の違いはそれほど大きくなく、違いは制度化のされ方の違いだけのような気もする。その一方で、課題に対するアプローチの仕方に何か違いがあるような気もする。上手い言い方がまだ見つからないが、自分が生きている社会と研究対象社会が異なる文化的背景を持ちながらも「地続き」で繋がっていて、互いに影響を及ぼしあっていることを常に意識しているような感覚のようなものが、地域研究者の特徴のような気がする。(西芳実)
- 地域研究の「構造」と「暗黙知」
今回の研究会で取り上げられた「暗黙知」「異分野・異業種」「映像」の話はどのようにつながるのかを考えてみた。
英語で書いた論文の原稿をネイティブ・チェックしてもらうと、「この部分は意味がわからない」とばっさり削られることがしばしばある。実は一番伝えたかったところが削られたりする。残ったのはほとんどが骨組みだけ。そうしないと英語を媒介にする多様な人たちには内容が伝わらないのだそうだ。コミュニティの枠を超えて伝えるには骨組みだけにするしかないし、骨組しか伝わらない。そこで切り捨てられるのは、書き手と理解を共有するコミュニティの人たちのあいだでのみ理解できるもので、「暗黙知」ということになるだろうか。骨組み以外の部分が切り捨てられ、骨組みしか伝わらないことに対抗するために、「自分は「暗黙知」を知っている」と言ってみたくもなるが、そういったところで相手には伝わらない。
地域研究の成果を他の学問分野や業種にどう伝えるか。他の学問分野でなされている「言葉づかい」を身につけることが大切だという意見には大きな反対はないけれど、でも「言葉づかい」だけでは用は足せないだろう。学問分野の習得を外国語の習得にたとえる考え方があったが、それに倣うならば、いくら英語ができて会話が成立していてもどうも当たり障りのない話にしかならないという経験がある。英語以外の言葉だともう少し深い話ができたりする。でも、これは英語自体に問題があるのではないだろう。英語以外の言葉で話をするということは、その言葉を使う特定のコミュニティのことを私がかなり知っているし、そのコミュニティに私が関心を持っているということだからだろう。つまり、言葉ができるだけではだめで、伝えるべき(あるいは引き出すべき)内容を持っていないと話にならないということだ。そうしないと、会話が成立したとしても、いつまでも骨組みばかりやり取りすることになりかねない。
最初の話とつなげると、他の学問分野に伝わるようにするときに必要なのは、「言葉づかい」ではなく骨組み(あるいは「構造」)なのではないのか。ただし、伝わるのは構造だけだったりする。地域研究では構造以外の部分が重んじられる傾向があるため、構造しか伝わらないとしたら地域研究の「味」はほとんど伝わらないということにもなりかねない。それはそうだが、そのことを口実にして、地域研究にも学術研究の一分野として当然備わっているはずの「構造」の部分をいい加減にしていることはないだろうか。「構造だけしか伝わらないのでは地域研究の意義が伝わりにくい」ということは認めるとしても、だからといって「地域研究では構造を取り出して伝えることはしない」ということにはならないはずだ。このような状況では、まず構造をきちんと伝えるにはどうすればいいか、その上で、構造から落ちてしまう部分をどう伝えるのかという二段構えで考える必要がある。
構造をどう伝えるのか。「言葉づかいがわからないために伝わらない」という言い方からは、聞き手の努力不足のような印象を受ける。確かに聞き手も努力は必要だろうが、伝える側の努力も必要だ。自分のコミュニティでしか通用しない伝え方のために伝わらないとしたら、それは伝える側の努力不足のためだろう。これを避けるためには、まずは伝える側が構造をきちんと把握するしかない。これまでの研究成果の蓄積を読みながら、そこに記された(あるいは隠された)構造を読み解くしかない。その意味で、「先行研究をどう読むか」は、地域研究の方法論の基本の1つなのである。言葉で積み重ねられてきたものはきちんと言葉で読み解き、それを言葉で伝えられるようにならなければならない。これをいい加減にしたままだと、言葉でのやり取りがきちんとできないことを棚に上げて、新しい技術が出てくるたびにそれに飛びつくことにもなりかねず、そうなったら何も積み重ねられないことになる。
では、「構造」から抜け落ちてしまう部分はどう伝えればいいのか。これを安易に「暗黙知」と呼ぶことで地域研究者に特権的な地位を与えるのとは違う方向で解決することがこの研究会で取り組む主な課題の1つであり、これについてはこれからさらに考えていきたい。(山本博之)
参加者アンケート
1.所属・立場・年齢
- 所属
東京大学・地域文化研究(2)
東京大学・教養学部(2)
東京大学・文化人類学(1)
東京大学・国際社会科学(1)
東京外国語大学(1)
日本学術振興会(1)
記入なし(1)
- 立場
修士課程(2)
博士課程(1)
大学院生(1)
学振特別研究員(1)
非常勤講師(1)
助教(1)
記入なし(2)
- 年齢
30代(2)
20代(1)
記入なし(6)
2.経歴
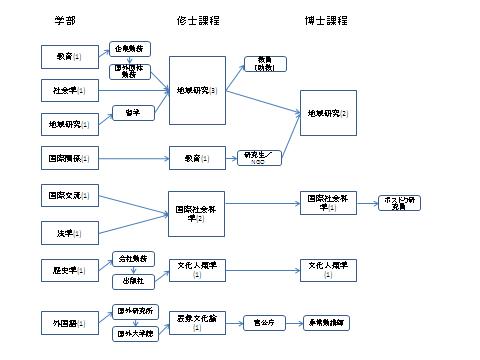
3.この研究会についての情報をどこで得たか(複数回答可)
- 友人・知人から(4)
- 学内のポスター・ちらしで(2)
- 学会のMLで(2)
- 学内のMLで(1)
4.この研究会への参加経験
- 2回目(前回参加は東大の第1回研究会)(5)
- はじめて(4)
5.どのような関心から研究会に参加したか
- 地域研のディシプリンとは何か。
- 比較政治学と地域研究のジレンマに発する苦しみ。
- 地域文化研究専攻(修士)に入ってディシプリンの問題(壁)をちょうど抱えていたので。ディシプリンとは何か、地域文化研究におけるディシプリンとは何かを明らかにしたかった。
- 地域研究という学問をどう理解し、研究を構築していくか。地域研究が実践にどう活用されていくか、していくか。
- NGOへの言及。
- 自分の関わる地域での研究手法を多様化させること。
- 映像の利用の方法論。
- 映像を使っての研究を行なっているため。
6.研究会に参加しての感想
- 興味深いです。
- それぞれの地域研究者の研究方法や悩みなどがわかって自分自身の研究を見直すきっかけになりました。
- 地域研究者として国際協力の現場に携わった際に地域研究者のもつSkillがどう活かせるのか(活かせるのではないかと漠然とした認識がありました)という大きな疑問をひとつ具体提起に言語化していただいたという印象を持ちました。
- 世代間での暗黙知についてNGOを事例として用いているのがおもしろかった。
- 前回(東大)よりもディシプリンとしてのあり方がわかったような気がします。
- 様々なディシプリンの人が読んでもわかる論述に肝があると思いました。
- 修士に入って4ヶ月。今までのもやもやとした感じが大分晴れました。ひとつのディシプリンだけからある地域を見るよりも、より柔軟な幅広い視野で地域を見ることができるのが、地域研究の良さ、魅力だと思いました(その分ディシプリンを学ぶ必要がありますが)。「修士まではものの見方を学ぶこと」という西先生のお話はとても参考になりました。NGOの実践と研究については、テーマとしてはあまり予期していなかったのですが、私自身NGOに参加していることもあり、非常に興味深く伺いました。研究会の開催ありがとうございました(地域文化研究専攻に修士課程の院生は30人ほどいるのですが参加が少なくて残念です)。
- 「暗黙知」の話自体はとても興味深いけれど、もう少し方向性を絞った方がすっきりするかもしれないという印象を持ちました。「地域研究者が特権的に知っている知識」の正体を暴いてほしいので、「暗黙知」が最初に使われた用法はあまり気にしなくてもよかったように思います。
(第2部)
- 談話会という形が面白いと思いました。
- 映像地域研究の確立の舞台裏がわかっておもしろかったです。
- 映像を研究に使おうとしている人たちの悩みがわかって興味深かった。でも研究に減点主義は似合わないと思う。
- 映像を使った具体的な研究手法の話がうかがえることを期待していましたが、映像の分類方法や撮影方法のお話が中心だったので研究手法としては物足りなさが残りました。
- 映像地域研究と映像人類学がどう違うのかが最後までわからなかった。
- 映像の話は質問と答えがまったくかみ合っていないやりとりが多かった。聞いていてまるで映像の撮り方講習会に参加しているかのような気持ちにさせられた。共通の前提がないと対話が成り立たない悪い例として興味深かった。
7.地域研究について日頃感じていること/考えていること
- 自分なりに地域研究の方法論をどう体系化するか。自分が今まで所属していた学問領域では地域研究的手法=人類学的手法と捉えられていて、地域研究=現地調査と見られている点について。
- 特殊と一般の緊張関係が創造的な研究にとって必要なのだと思うので、これから先も対象地域と向き合っていくと思います。
- 例えばミャンマーなどでデモが起きればニュースですぐ大学の地域研究者が説明しているインタビューを聞いていたので、それと重なって西さんが提案した地域研究者の意義はおもしろかった。
- 他の学問分野の人に地域研究について伝える(意義、設定した課題など)際に、やはりある程度伝えるための「言葉」(相手のディシプリンが使用している「言語」)を知る必要があるということを感じています。地域研究をしている周囲の学生は何となく似たような感覚(フレキシブル、オープン)をもっている・・・ような印象があります(ポジティブな意味で)。
- NGO活動でも映像の利用でも、どうしてそれを扱うのかについて無自覚で、「そこにあるから利用したい」「とにかくよいものだから紹介したい」と語ろうとする人が多い。地域研究の手法を考えるなら、事例をどう処理するかではなく、その事例を扱うことにどういう意義があるかを示す方法であるべき。
- 地域研究をディシプリンの下請けのように見る見方があるけれど、実際は逆ではないのか。院生の発表でときどきデータばかり細かく論がない発表や質疑を見るが、こういう(悪い意味での)「地域研究的」な発表を見ると、学生時代にはまずどれかのディシプリンを学ばせてどれでもいいので枠組みを作らせて、上級に進んだ人たちが地域研究を行うという考え方の方がいいのではないか。
8.この研究会への要望
- 地域研究の優れた研究のレビュー。
- 研究手法が多様であることこそが地域研究の特徴であるという議論をしてもよいのではないか。
- 地域研究の方法論というと教官の事例研究を並べたものになりがちなので、方法を本気で考えるこのような研究会はとてもありがたいです。バランスのとれた報告と十分な討論で非常にためになるので、このままの形でぜひ続けていってほしいと思います。
- 小森先生の「暗黙知」の図式化のように、地域研究のoverviewを図式化したらどうでしょうか?(もうされていたらスミマセン)研究者それぞれイメージしているモノが違うので、言葉で伝えようとしても抽象的なので、それについて話すのは少し時間がもったいないような気がしました。特に研究をはじめたばかりの学生にとっては自分の立ち位置がわかってよいと思います。
- 大学院生がもっとたくさん参加できるように開催大学との事前の連絡と案内を十分してもらえたらと思います。